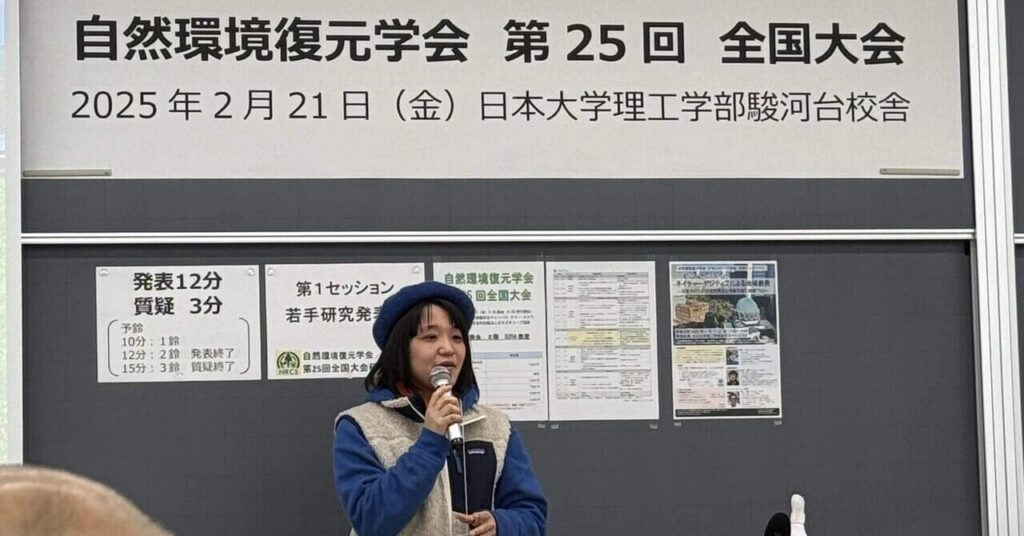
今日は、東京・お茶の水にある、日本大学理工学部キャンパスにて、自然環境復元学会に参加しました!
「牛とヒトが協働した新たな環境再生型農業の実践例」
というタイトルで、長崎の森川放牧畜産での牛の放牧による環境再生の取り組みについて発表させていただきました。
植物の生態系などの演題が多い中、動物の放牧というのは珍しかったようでしたが、
「明るい未来を想像させるワクワクする取り組み」
「動物が自然に還ることで、環境再生ができる」
という点に、ご興味を持っていただきました。
民家の中での放牧は、地域的なハードルが高い一方で、例えば行政の管理下にある河川敷での放牧は可能なのか、といった質問や、
どのくらいの広さに何頭くらい放牧可能なのか、
他の地域で実践するとしたらどうか
と言った質問もいただきました。
また、私の宇宙惑星科学で博士号を取得したものの、牛の放牧現場に関わっているという経歴も驚かれました、笑
一方で、環境再生と持続可能な地域づくりという点では、
中山間地域、里山保全が急ぎだということが、現場に入らないとなかなか理解できないということも感じました。
千葉県館山市でヤマナハウスという里山保全コミュニティを運営されている、沖浩志さんも、「シェア里山を外部の力で保全する」というタイトルで発表されていました。
ヤマナハウスについて – YAMANA HOUSE – 南房総三芳のシェア里山 ヤマナハウスについてヤマナハウスとは地域とのつながりメディア掲載ヤマナハウスとはヤマナハウスは、有志によって運営されているシェア里山です。ヤマyamanahouse.site
現場にいると、里山保全が環境再生の根本で、地域の実践知を持つ方の高齢化を考えると、
その技術や知恵の継承が急ぎだということを痛感する。それをどう伝えるかを必死に考えている、と仰っていました。
私は研究がしたいわけではなく、
ただ、博士号を持つ一人の人間として、
今関わっている長崎の現場の農家さんや知恵や技術、この重要な取り組みをどうバックアップできるか。
若い人が現場に関わるにはどうしたらいいのか。
次の世代につないでいくために、
ただそれがしたい。
里山の現場を知らない人たちが、どんどん増えていくなかで、
現場と学術会や行政をつなぐことが、今後ますます必要になる。
課題は山積みだけど、まずは今日、ここからスタートだと思いました。
次は学会誌に論文を投稿したいと思います。
一つ一つ、できることをやっていきます!

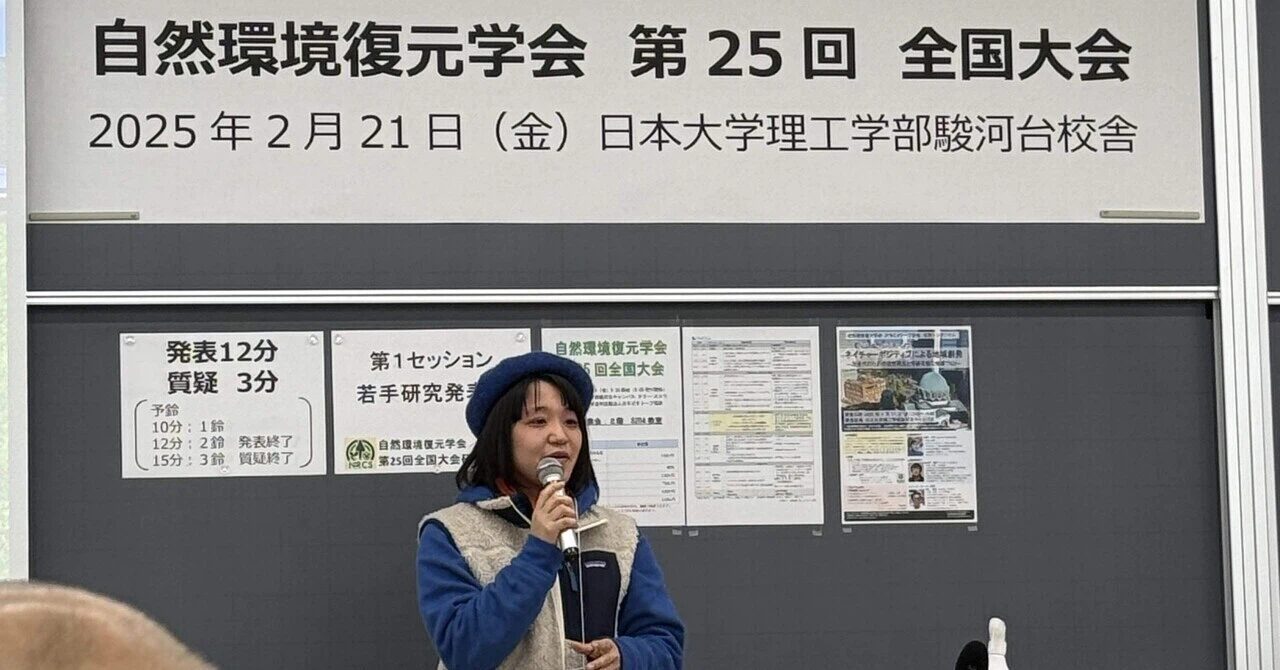


コメント